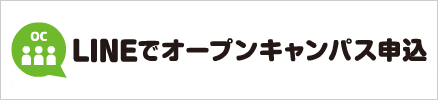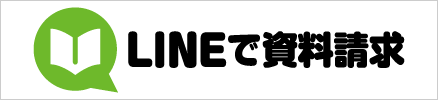理学療法学科では、まずは理学療法の基本に加え、社会福祉の基本知識も習得。見学実習では理学療法士の役割・業務を学び、実践的な授業でソーシャルワークも学びます。3年次以降は障がいの予防と治療に関する知識・技術習得のための運動療法演習や評価実習・総合実習で治療のための多様な知識と実践力を医療現場で身につけます。


スポーツ医学検定は、『スポーツのケガを減らし、笑顔を増やす』を理念に、スポーツが広く根付く社会を築くには、トップレベルのアスリートのみではなく、子どもから高齢者までが安全で楽しくスポーツに取り組める環境が必要で、より安全でケガの少ないスポーツ環境を作るため、メディカル関係者が持つスポーツ医学の知識を、スポーツ指導者、スポーツ選手の保護者、マネージャー、そしてスポーツ選手自身に広めたいと考え誕生しました。
本校理学療法学科では理学療法士としてスポーツに関わりたいと考えている希望者を対象とした検定試験合格に向けた講座を特別授業として開講して全力でサポートします。




他校とここが違う!6つのメリット
東京福祉大学の卒業資格を取得し大卒として就職ができる!
全員受験・全員合格をめざした国家試験対策!
東京福祉大学の科目で、理学療法の専門家にも必要な介護保険など福祉の知識が学べる
クラス担任制による親身な指導
臨床経験豊富な先生(認定理学療法士)から実践的な知識・技術を学べる
※認定理学療法士は理学療法士協会の認める上位資格となります。
文部科学大臣認定の職業実践専門課程
学習の特色
大卒+αの力を身に付け、現場に強い理学療法士に!
4年間の授業で、理学療法専門科目と福祉系大学科目を修得します。
これにより、多くの現場で必要とされる高い技術をもった理学療法士をめざすことができます。
理学療法専門科目
理学療法の理論を理解し、必要な知識や技術を修得します。また、国家試験に向け徹底した指導、本学園独自の国家試験対策講座により、難関の国家試験に合格する力を身につけることができます。


福祉系大学科目
東京福祉大学のカリキュラムによって、介護保険制度やソーシャルワーク理論など、リハビリテーションにも必要な社会福祉についても学ぶことができます。
福祉に強い!+ 現場に強い!+ レベルの高い!
理学療法士に!!
1ランク上の専門家として活躍できる!
大学の学習で身に付けた福祉領域の知識を患者様やご家族の対応に生かせる。
カルテや報告書書類を作成する高い文章力が身に付いている。
最新の医療機器の使用技術に精通し卒業後も本校の設備を活用しながらリハビリを行える。
患者様にあったリハビリ計画を立案できる思考力、問題発見・解決能力が身に付いている。

令和5年度 卒業生就職実績

卒業生の就職先(抜粋)
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター/岐阜市民病院/医療法人はなみずき はなみずき整形外科スポーツクリニック/社会医療法人杏嶺会 一宮西病院/社団法人日本海員掖済会名古屋掖済会病院/横浜なみきリハビリテーション病院/医療法人大朋会 岡崎共立病院/医療法人社団綾和会 浜松南病院/医療法人聖生会 介護老人保健施設リハビリス井の森/医療法人富田浜病院/社会福祉法人 岡崎市福祉事業団/リハビリ専門デイリーサービスみなもと など
卒業生の主な取得資格
主な就職先(業種)
など
理学療法士の魅力
起きあがる、座る、立つなどの基本動作・機能回復を目的に、運動療法、電気・光線治療、マッサージなどの物理療法を行う理学療法士。
高齢化社会が訪れた現在は、医療現場以外でも福祉施設などに活躍の場が広がっています。
理学療法士とは? さまざまな物理療法を行うリハビリテーション専門職

理学療法士(Physical Therapist, PT)は、医療従事者の一員であり、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士とともに、リハビリテーション専門職と称されるうちの一つであり、国家資格です。
理学療法士の仕事は、理学療法を受けている患者様、障害者の方々から「歩けるようになった」、「回復して退院することができた」、「ありがとう、良くなりました」などと笑顔を見せてもらえた時に「やりがい」を感じます。
身体に障害を抱えてしまった人たちと真正面から向き合い、信頼関係を築き、一緒になって障害を受け入れ(障害受容)、家族も含めてサポートをします。患者様が本格的な社会復帰をする際は、作業療法士にバトンタッチしてリハビリを続けます。
理学療法士の就職は? 資格を武器に、安定した生活ができる!

本校には毎年700件を超える求人が来ているため、新卒で就職先を探す際も一般企業より探しやすい状況にあります。また、諸事情により転職する場合も、「理学療法士」の資格を持っていることで、新たな職場を見つけやすくなります。
また、理学療法士を募集している病院、法人、施設などは決まったエリアにあることが多いので、引っ越しを伴う転勤は少なく、安定した生活ができる傾向にあります。
理学療法士の収入は? 大卒の学歴と資格手当で手取りアップの可能性大!
理学療法士の基本給は一般企業との差はほとんどありません。そして東京福祉大学卒業資格と理学療法士の国家資格を取ることで2万~4万円の資格手当が出る病院、施設が多くなっています。
充実した国家試験対策【2023年度実施例】
1~2年次
- 通常授業で医療の基礎知識・学力を身につける
- 1年次から模擬試験開始(模擬試験は1~3年次で実施)
3年次
- 国家試験の過去問題を取り入れた授業・課題を展開
4年次
◆国家試験対策講座
◆国家試験模擬試験
- 受験日直前の2月下旬まで開講
- 長期休暇期間(冬休み)にも集中講義を開講
- 平日夜間、土曜・日曜・祝日も開講
国家試験
試験日
2月下旬~3月上旬
(4年次に卒業見込みで受験)
合格発表
3月下旬
※万一合格できなかった場合、卒業後も対策講座が受講できる
注目の最新設備「Vicon」を自由に使えます!

VICONは、オックスフォード大学が開発した3次元動作解析器、いわゆるモーションキャプチャーです。皆さんもゲームや映画のCGを作成する時に全身に銀色のボールを着けている人がたくさんのカメラの中で動いているのを見たことがありませんか?
この機械は、人間や動物など様々な動くものを科学的に解析して、例えば人間であればどこの関節に負担がかかっているかなどを客観的に見るものです。
VICONではこんなことができる!
-
人の様々な姿勢を分析
-
関節の可動域の視覚化
-
人がバランスを取る際の筋肉の動きを可視化
など
他にも医療現場で使用する機器がたくさん!

呼気ガス分析装置
運動中の息(酸素摂取量や二酸化炭素の排泄量など)を測定し心肺能力をみる装置。バイク(自転車)と連動して、負荷がかかった状態の呼気ガスを測定することもできます。スポーツ指導でもよく使われています。

超音波画像診断装置(エコー)
超音波を用いて体内の病変を調べる検査機器。普通に病院に置かれている機器です。体表から体内に超音波を発信し、そこから戻ってくる反射波(エコー)をコンピュータ処理し、画像化します。その画像上のコンストラストから、筋や筋肉の動き、病変の有無を確認します。

筋電位計
筋肉が収縮する際に発生する微弱な電気を読み取り測定することで、筋力を図ったり筋機能を分析したりします。リハビリテーションの分野やスポーツ科学の分野で広く使われています。本校の筋電位計は一度に多くの筋肉を測れる最新のものを使用しています。

圧力分布測定システム
薄いセンサーシートの上に座ったり寝転んだりすることで、体圧の分布を測定し、その結果をPC画面上でさまざまな形で表示、分析するシステムです。寝たきりのお年寄りの床ずれの予防や、リハビリテーションに役立てます。
MESSAGE
from student
理学・作業名古屋専門学校 理学療法学科 4年
真田 康陽さん
至学館高等学校(愛知県) 出身

学生が授業に参加しやすいのが本校のよさ。
キャンパスライフも充実しています。
本校の授業のいいところは、学生が自ら挙手できなくても先生が指名してくださることで、授業に参加しやすくなることです。授業中に先生が話す学生時代のエピソードやリアルな現場の話は、聞いていて楽しいですし、ためになります。
実習では、現場の理学療法士の仕事の様子を見学し、患者さんに合わせてアプローチを変える理学療法士さんの姿勢にふれたことがとても印象深かったです。また、授業では、過去の国家試験に出た内容を伝えてくださるほか、国家試験対策講座では実際のテストに似た問題をつくってくださるので、試験本番をイメージしやすく勉強がはかどります。
クラスメイトとはとても仲がよく、一緒に復習や課題をしたり、わからないところを教え合ったり、空いた時間には遊んだりしています。入学時はコロナ禍で学内イベントもありませんでしたが、コロナ禍が明けた昨年はスポーツ大会を楽しむことができ、大切な思い出になりました。
理学・作業名古屋専門学校のここが好き!
一番いいところは立地のよさ。名古屋、栄、伏見、久屋大通からアクセスしやすく、学校帰りや空いた時間にご飯を食べに行ったり遊んだり、アルバイトしたりといった活動がしやすいのがうれしいです。
from ex-student

理学療法士 学士(社会福祉学)
生駒 和さん
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 勤
務/理学療法学科 2021年3月卒業/愛知県立
知立高等学校 出身
患者さんが「相談してよかった」と思える理学療法士をめざしています。
私は中学・高校時代に部活動でけがをしてリハビリを受けることが多く、そこで理学療法士の方と話すうちにこの仕事に興味を持つようになりました。
今の職場にはさまざまな疾患の患者様が入院されていますが、その症状や訴えは一人ひとり異なり、必要となるリハビリも求められる知識や技術も変わってきます。また、認知機能が低下している方や高次脳
機能障害のある方とのコミュニケーションや運動指導などに難しさを感じるなど、悩むこともたくさんあります。でも、昨日まで患者様お一人ではできなかったことができるようになる場面に立ち合うなど、うれしさややりがいを感じる瞬間も多いです。
理学療法士はご高齢の方の自立した生活をサポートし、生活の質の向上に貢献することができる仕事。本校では多くを学び、その職業に就くための準備を十分することができます。日々、患者様と接する時間の長い理学療法士として、「この人なら相談できる」「相談してよかった」と思える存在になりたいです。